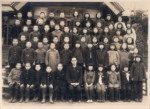
テーマ 石巻市立門脇小学校6年3組/宮城県石巻市(昭和27年3月撮影)昭37卒 大森 昭啓
私は3歳から15歳までの幼・少年期を父が赴任していた宮城県石巻市で育ちました。通学した小学校は「石巻市立門脇(かどのわき)小学校」でした。
卒業した昭和27 年当時は未だ国全体が貧しく、所謂ニコヨンの時代でした。写真も高価で、卒業アルバムと言っても、学年全体3クラス分の写真はなく、教職員と当該クラスの2枚の写真が貼ってあるだけのささやかなものでした。
あの平成23年3月11日、テレビから聞こえてきた「日和山から中継です」の声。
「この山の下の学校が燃えております」。―――――――見ると炎が吹き上がっておりました。
この下の学校なら門脇小学校?だけど鉄筋コンクリートが燃えるの?机や椅子があるからかな?・・・だ
けど火の気はないだろうに・・・」。
取り留めのない事が頭をよぎりました。
津波で押し寄せられた自動車から漏れたガソリンに火が着き、大災害の中で消火活動も出来ず、3日間燃
え続けたとのことでした。
平成27年3月22日最後の卒業式を行い、同31日、142年間の歴史を閉じました。
尚、この卒業写真に写っている人々の中で、「3.11」で亡くなった人はいないと聞いております。
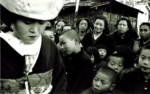
テーマ 花嫁さんだー/新潟県小千谷市(昭和30年1955.11撮影)昭32卒 野中 昭夫
2年生の秋帰省。実家の前の道でお嫁さんに出会った。嫁ぐ人を見送る隣人たちの真剣な、何か心配そうだが温かい視線が嬉しかった。
終戦から10年、新しい昭和時代への微笑なのだろう。
当時この地には結婚式場なんかなかった。
今宵は「祝言」。両家集いて三々九度の杯を挙げて結婚を祝うことだろう。
昭和19年春,招集された父を同じ道で、軍歌で送り出した。その時の後ろ姿が思い出された。
確かに昭和は変わった。

テーマ 那覇・桜坂の夜/沖縄 (昭和41年撮影)昭32卒 徳永 善彦
沖縄が日本に復帰する以前の昭和41年、林忠彦先生と今は亡き広島の写友たちとの沖縄撮影旅行で撮った一枚です。
那覇の歓楽街「桜坂」の夜更け、皆と立ち寄ったバーを出た道端で蛇皮線を爪弾きながら堪らなく哀愁を帯びた琉球民謡を歌う盲目の男が座っていました。
4、5カット撮らせてもらいましたが、不自由な身の彼のことを思い、ずっと発表を差し控えてきましたが、既に半世紀も歳月が経過し、昭和の沖縄の歴史の一駒として、私の所属している二科会写真部60周年記念写真集へ先年敢えて発表させていただいた写真です。

テーマ 三池炭鉱・三川坑跡/福岡県大牟田市 (平成28年10月3日撮影)昭45卒 白谷 達也
昭和38年(1963年)11月9日午後3時12分、三川坑第一斜坑内で炭じん爆発が発生し、死者458名、一酸化(CO)中毒患者839名を出した。
丁度その頃、僕は西鉄大牟田駅頭に立っていた。
駅周辺には人も車も見当たらなかった。「ゴーストタウン」という言葉がよぎった。
あれから54年後、昨年10月閉山した三川坑跡に立っていた。
しかし、第一斜坑は坑口もろとも埋められて更地になっていた。
まるで何も無かったかのように。
有明海の海底深くまで「人車」で坑夫たちを送り込み、「炭車」で石炭を運び上げてきた鉄路は辛うじて残っていた。
事故当時第一斜坑に下りていた約1400名の坑夫たちが通って行った路に違いなかった。
CO患者は今でも後遺症に苦しんでいる。

自由 ひとり・木道を行く/クロアチア プリトヴィッツェ国立公園 昭30卒 工藤 司朗
世界遺産「プリトヴィツェ湖群国立公園」はクロアチアを代表する観光地で、当然多くの観光客で賑わいます。
その静寂な公園を表現する写真を撮るのは至難なことでした。
人の賑わいが去るのをしばらく待ち、カーブを描いた美しい木道に一人の女性が差し掛かりましたのでシャッターを切りました。
静寂な公園を撮るにしても“人”を入れることが条件と考えたからです。この広い公園で数百枚を撮りましたが、計算して撮れた唯一の作品です。

自由 塩を運ぶ/エチオピア ダナキル砂漠 昭31卒 稲村 不二雄
海抜マイナス120メートル、乾季になると気温は50度、エチオピア北東部に広がるダナキル砂漠は「地球上で最も過酷な地域」と云われている。その砂漠のなかを、採塩場のアフデラ塩湖から200キロ離れた、標高2000メートルのメケレの街まで2週間かけて塩を運ぶらくだの一群がいる。一頭が250Kの岩塩を背負い、数10頭が集団で歩く。
ダナキル砂漠に野営し、らくだの一団を探すために、トヨタの4WDを使って広大なダナキル砂漠を何時間も走り回る。乾季に入った11月だったが2017年雨季の雨量が多く岩盤砂漠は巨大な湖状態になっていた。現地ガイドさんが視力3.0を活かし遥か彼方の一団をやっと見つけてくれた。じゃぶじゃぶと水を蹴散らして歩くらくだの行列は壮観だった。1000年以上以前から続けられていたこの仕事も、近代化に伴い間もなく終了するらしい。歴史に残る姿を見られたのは幸運だった。

自由 師匠と弟子/東京 王子稲荷神社 昭33卒 浅澤 尭
毎年、大晦日の夜、王子の街は狐になった人々であふれかえります。
狐になった人々は行列をつくって「ゑの木衣装稲荷神社」を出発し王子稲荷神社」に向かいます。
二月、「王子稲荷神社」の「二の午祭」には近隣の幼稚園の園児たちが牛乳パックで造った狐のお面をかぶり神社に集まってきます。
この神社で特に子供たちに人気があるのはお獅子のおじさんです。
体が柔らかいのが自慢のおじさんは、足を百八十度に開き、園ごとの記念写真にすべて参加します。
ある年、このおじさんに嬉しいことが起こりました。自分の芸を引き継いでくれるお弟子ができたのです。
園児たちが、帰った後にお獅子の芸の特訓が始まりました。時には観客の笑いを誘うような動きを見せなくてはなりません。
恥ずかしさで真っ赤になりながら師匠の真似をする若者。
いい写真が撮れた!!
どうしてもこの写真をお獅子のおじさんに差し上げたいと思っておりましたところ、大晦日の「狐の行列」で狐になったおじさんに出会いました。
なんとおじさんは「王子狐の行列の会代表」だったのです。創業八十年の老舗メンズファッション「菊秀」の社長 高橋秀一さんでした。
でも2年後、このお弟子は家庭の事情でおじさんのもとを去っていきました。後継者を失ったおじさんの落胆の様子が今でも忘れられません。

自由 斜陽/志賀草津道路山田峠付近 昭33卒 高木 實
志賀高原から横手山を越え、早春の上信国境尾根にスキーを走らせ、振り子沢を草津に滑り下りた。
山田峠まで来た時、陽は西に傾き、雪のピークが逆光に映え、誠に写真的なシーンを造り出していた。
季節や天候などの移ろいとともに、自然は刻々と表情を変え、撮影の瞬間、どんな姿を見せるのか予測はできない。
カメラポジションと構図を決めて、イメージ通りの画面ができるよう自然が応えてくれることを祈りつつ、四季の山々に通い詰めた日々のこの一枚。
ファインダーを覗くと、イメージと寸分違わぬ画面ができ上がっていた。
私の頭の中を、自然が読み取ってくれたのかも知れません。

自由 日本の光/軽井沢、六本木 昭35卒 出井 伸之
光にはパワーがある。
都会の春の光の勢い。
森の冬の朝陽。
私たちは太古より光を頼りに生活して来た。日本の未来をより輝かしいものにする為に、「自然」の光を大切にしていきたい。

自由 いのちのビザ/早稲田大学商学部前 昭35卒 平山 恵章
「命のビザ」で世界にその名を知られる杉原千畝氏を私が知ったのは、氏がテレビなどで取り上げられる以前のことだった。
ご遺族のお一人と妻がたまたま知己であり、氏は既に他界されていたが、その人となりは仄聞ではあるが伺っていた。
氏の業績への評価は、ここ数年一時ほどの熱狂を持たれていないと私は感じているが、日本国内では連日のように「忖度」と言う言葉が新聞紙面を賑わし、世界では物理的にも精神的にも「難民、移民排除のための壁」が築かれようとしている今こそ、杉原千畝氏の功績をじっくりと振り返る必要があると私は考える。
氏は、優れた外交官であるがゆえに「忖度」などはせず、むしろ本国外務省の意に反し自らの考えの下「命のビザ」を発給した。それはその人の命を賭した行為であったと思う。
難民を排除するのではなく、受け入れる決断をしたことは、世界を取り巻く今の情況を考えると、一層賞賛されるべきものだ。
氏の功績を称えた記念碑を早稲田大学構内に撮りに行った際、その碑のある場所はひっそりとしており、近くを通る学生にもその場所は知られていなかったが、それこそが慎ましやかに自らの功を誇らなかった彼の人柄にふさわしいと感じた次第である。

自由 鳥に訊けースズメ/北海道白老町 昭45卒 渡辺 新平
父母が晩年を暮らした家の前の道、そこに驟雨が襲い、あっという間に小さな水たまりをつくり上げた。直ぐさま、雀たちがやってきて水浴びを始めた。
普通に人が、車が行き来する道である。
「何故そんなところで」と「鳥に訊いた」。「このあたりは温泉水ばかりで、普通の水場がないんだよ。天からの贈り物の雨水も、最近は汚染物質とかいうやつが混じっているけどね、習性だからね。キレイになって生き延びたいと思ってさ」。
たまにだが、こういう錯覚が鳥との繋がりの機縁となり、共生する世界を垣間見ることになる。
バラバラにやってきて、それぞれに場を占め、一斉に水浴びする。路上の水たまりは雀たちの蘇生の舞台である。

自由 極楽浄土が見えた/東京 稲城市 昭46卒 石崎 幸治
写真の大きな役割の一つに物事を記録することがある。人物や風景写真を見ることができて、居ながらにして色々な人に会えるし、世界中を訪れることもできる。でも最近、そのような役割・機能にあまり感動を覚えない。
不遜ながら、その場に立ってシャッター・ボタンを押せば同じような写真を撮れると思ってしまう。写真には絵画のようなタッチがないから、独自の表現法を創り出すのが難しい。
写真は早いシャッター速度で撮影すると被写体の動きを止めることができる。また接写すると小さい世界を記録することができる。この2つの特性を活かして、水滴が水面に落ちて跳ね上がる瞬間を撮影した。
一瞬の水滴の形とその中に花が映っている姿を肉眼では見ることはできない。これからも写真を見た瞬間に「綺麗」とか「不思議」さを感じさせる独自の世界を撮り続けたいと願っている。

自由 秋色/広島市東区馬木 昭47卒 岩崎 洋一郎
私の写真は概ねとても不真面目だ。しかし、自分の家の庭先で量産できるこのやり方は、日々の小銭稼ぎの仕事に追われる私にとっては今や唯一の生き甲斐となっている。
さて、仕掛けはこうだ。先ずはマクロレンズを浮き浮きした気持ちでカメラに取り着ける。そして、葉っぱとトンボを用意する。順序は逆でも問題ない。
トンボは猫の額ほどもない自宅の古池からいくらでも調達できる。が、決して乱暴に扱ってはならない。トンボは迷惑千万と思っているので、丁重に接する心構えが大切なのだ。
これはある時以来、昆虫撮りの礼儀と固く信じるようになった。ここでの必需品は虫取り網。これが無くては「逃げる・追う」のイタチごっこがまるでできない。
「ごっこ」が都合よく行き、運よくこちらの意図する形になったら、その一瞬を決して逃さないこと。
連写!連写! むろん、キツイ逆光とバック紙も必需品であることは言うまでもない。
最後に大恩人のトンボさまを元の池にそっと戻して差し上げることを絶対に忘れてはならない。

自由 毛皮を争奪するタジク人の男達/中国新疆ウイグル自治区タシュクルガン 昭47卒 岩崎 洋一郎
羊(山羊?)の毛皮を奪い合う騎馬競技の舞台となっているのは、中国新疆ウイグル自治区でも最西端に位置するタシュクルガンで、そこはタジク族の世界。
背景の雪山を越えればもうタジキスタンで、タジク族の居住地域は、更にアフガニスタン、ウズベキスタンと広がっている。
しかし新疆だけに限ればその人口は僅か数万人に過ぎず、千数百万人のウイグル族と比べると圧倒的に少数民族で、他にも20近くの少数民族が存在している。
全中国から見ればウイグル族も少数民族で、政治的、宗教的な束縛を受けているが、新疆に関して言えば多数派となり、タジク族等の少数派と様々な確執を生じており、人為的に民族を分断する国境線の理不尽さを痛感する。
写真の競技はアフガニスタンでは国技のブズカシと呼ばれるが、男達の必死の形相は懸命に民族のアイデンティティーを主張しているようにも見える。

自由 トラバース/北アルプス 朝日岳 昭48卒 稲山 正人
登山口の蓮華温泉から湿原を抜け、雪融けの急流を渡渉し、樹林帯の急登を登り切ると森林限界に達した。登山道は木道となり私を草原に導いていく。ここまで3時間。草原の向こうに目指す朝日岳が見えている。行程はまだ半分に満たない。
2017年7月中旬、私は梅雨前線が停滞する北アルプス白馬岳を目指して蓮華温泉から入山した。草原を囲む山の斜面はまだ分厚い残雪に覆われている。その雪面からは靄が燃えたち、神秘の世界を演じている。傾斜した残雪帯の先端からは雪解けの水が滴り落ち、やがて水流となって草原を潤す。その草原では水音を背に小さな花たちが一斉に咲き始めている。この時期の北アルプスの北部は雪山から夏山へ移り変わる幕間である。雪が融け、山肌が表れ、花が咲き始める。
足元に咲く花々を見ていると実にお行儀がいい。岩間、水辺、砂礫、樹林帯、と皆おとなしく自分の住む場所をわきまえている。闖入者の私は花たちと無言の挨拶をかわしながら丁寧に歩を進める。
やがて高度2千メートルあたりから完全に雪渓歩きとなる。長い雪上のトラバース道が尾根へ続いている。ここは慎重にアイゼンをつけ、サクサクと確実に高度をあげていく。
やがて雪渓は消えて、ガレ道となった。とうとう朝日岳直下の尾根に登り詰めたことを確信。今日の目的地、朝日小屋はもうすぐだ。

自由 秋色/北陸地方の某寺 昭50卒 湯川 登紀雄
・秋雨前線の停滞であいにくの天候のなかを、北陸地方の寺社を巡る??。コートを着込んでも冷気が染み入り、カメラを持つ手がかじかむほどだった。
・名もないお寺の境内に足を踏み入れると、朱色と黄色の織りなすじゅうたんが広がっていた。
思わずシャッターを切り、さらに撮り続けようとしたが、あとから来た参詣者に追い越され、じゅうたんが綻び始めてしまった。前後に動いたりアングルを変えてみたりしたが、どうしても納得がゆかない。
・あれよあれよという間に、じゅうたんのほころびが広がって、最初の感動の余韻だけが脳裏に漂っているのであった。

自由 sarabande/川崎 昭60卒 東 俊治
バッハのリュート組曲BWV997の3番目に配置されている曲からの発想です。
壁やフェンス、いくつもの通信網にがんじがらめにされて、いつの間にか真実から乖離した闇の中で生活している我々の日常。
そんな中でふと我に返り、遠く虚空にある光の中に、希望を形にして見出せるのかと問い続ける人間の性を表現いたしました。

/3104545807.jpg)





/3636084576.jpg)



/2575972565.jpg)

02/3870095614.jpg)





/2757968325.jpg)



/3650670302.jpg)
Scan20002/229808107.jpg)

















